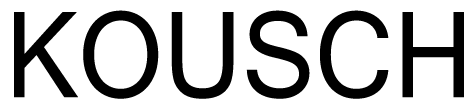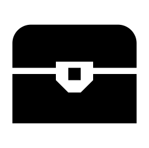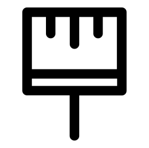デザインTシャツ【コウシュ】のブログ
シルクスクリーンを取り扱うブランドのブログとして決して避けて通ることのできないテーマ
– アンディ・ウォーホル(1928-1987)について。
(シルクスクリーンと現代アートとの関係はこちら)
アンディ・ウォーホルといえば、
マリリン・モンローのシルクスクリーン版画や、キャンベルスープをモチーフとした作品が真っ先に思い浮かぶが、
はて、これがアート?作者は何を考えてこれを作ったのか、
この良さがわからないのはこれを見る自分のせいなのだろうか、と少なからず思わせがちである。
ウォーホルについて紐解いてみると、
冷血漢のように見えた側面と温かく人間味あふれる側面、
何も考えておらず表面的であるように徹したこと、それが、意図してなのか、意図せずなのか、はたまたどちらともなのか、ということ、
そして、1968年、40歳のときに拳銃で狙撃され弾丸が内臓を貫通するという出来事を境にそれ以前、それ以降とで人が違ってしまい、
また世間の評価も変わっていったこと、
これらがウォーホルをますますわからなくさせる原因のようである。
ただ1つ、明らかなのは、
「はて、これがアート?作者は何を考えてこれを作ったのか」というものをアートの歴史上に登場させたこと、
それから、
ウォーホルは自分が生きているその様自体をアートとして作り上げようとしたのだろうということ。
ウォーホルの1つ1つの作品について無理に解釈するよりも、
ウォーホルの作品、生き様の全体を眺めてみたほうがずっとわかりやすく
その美のセンスが見えてくる。
もう少し詳しく見ていこう。
彼は冷血漢だったのか、人間味あふれる人物だったのか
ウォーホルがかつて熱烈に可愛がっていたミューズ、イーディ・セジウィックが死んだとき、
「Who’s that?」とまったく無関心の(であるような)発言をし、
ウォーホルのシルバー・ファクトリーの常連であったダンサー、フレディ・ハーコが
薬のせいで5階からジャンプして死亡すると、
カメラを回しておくんだった、
と言ったという。
しかし、これはウォーホル特有の感情のごまかし方で
「He tried to be campy. He had a very weird sense of humor. 」と助手がコメントしている。
母の死については、
「ママはブルーミングデールズ(デパート)に行ってるよ」
とその後ずっと言っていたようである(これはいけてる)。
他方、年上のいとこたちは、「私たち(アンディも含め)って変わり者だったの、おもしろいことをいつも見つけて笑ってたの」、
ウォーホルに可愛がられていたポップアートの寵児達、キース・ヘリング、バスキアは
ウォーホルを心の底から慕っていた。
おそらく、本当は温かみがあり不器用な人物であるものの、
それを必ずしも周りに見せなかったということではないか。
その背景を、
見かけが気持ち悪く、コンプレックスがあったから、とか、
広告業界で感情を捨てて仕事せざるを得なかったから、とか、探る動きもあるようだが、
ここでは取り上げないことにする。
私たちのまわりにだって変な人、冷たい人はいる、でも温かい側面もある、
ウォーホルも決して聖人や徹底した変人ではなく、
普通の、いやちょっと変わった、人だったということだ。
何も考えておらず表面的であるよう徹したこと、これは意図してだったのか、意図せずしてだったのか、はたまたどちらともだったのか
アンディ・ウォーホルが突撃インタビューされている映像を見ると、
殆どと言ってよいほど、隣に誰かがおり(美女であることも多い)、
インタビュアーに何かを聞かれても、たいてい、「Yes」「No」のみか、
「うーん、〇〇(隣の人の名)、どう思う?」と言って、自分では何も答えていない。
また、彼は映像作品を多数撮っているが、
撮影された人々は、ウォーホルは何も指示しなかった、
ガイダンスを求めても、何のアイディアもないようだった、と言っている。
シルクスクリーン作品については、
自分で刷ったものもあるようだが、
シルバー・ファクトリーのお抱えの刷り師や少し離れたところにある印刷所の刷り職人たちに電話で指示して完成させたものもあり、
その版画はいったい誰の作品なのか、という定義を困難にした。
有名なBrillo Box(洗剤の箱)や
32種類の味のキャンベル・スープの缶詰をそれぞれ1つずつキャンバスに描いた32枚の作品
に代表されるような工業製品を再現した作品は、
ウォーホルというアーティストでなくても、誰にでも作ることができる、と思わせる。
ただ、その作家の存在を消すということこそがアンディ・ウォーホルの意図であり、
“…No one would know whether my picture was mine or somebody else’s.”
“It would turn art history upside down?”
“Yes.”
そこに自分の好きなもの、美しいと思うもの、興味あるもの、あこがれるもの、をミックスさせて作品を
つくったのであろう。
実際、アンディ・ウォーホルはキャンベル・スープを毎日食べて育っており、
それがママの味だったのだ。
大人になっても毎日食べ続け、
自宅を訪れたゲストのもてなしの際も自らキャンベル・スープの缶をあけてごちそうした、
という逸話がある。
コカコーラにも、
”What’s great about this country is that America started the tradition
where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest.
You can be watching TV and see Coca-Cola, and you know that
the President drinks Coca-Cola, Liz Taylor drinks Coca-Cola, and just think,
you can drink Coca-Cola, too.
A Coke is a Coke and no amount of money can get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking.
All the Cokes are the same and all the Cokes are good.
Liz Taylor knows it, the President knows it, the bum knows it, and you know it.”
という思い入れがあった。
1968年の狙撃事件の前と後
ウォーホルのシルバー・ファクトリーの常連でウォーホルの映像作品にも女優として出たことのあったバレリー・ソラナスは
妄想型統合失調症ということもあって逆恨みで、1968年6月、ウォーホルを撃つ。
弾丸は複数の内臓を貫通しウォーホルは重体となったが、一命をとりとめた。
シルバー・ファクトリーは、アンディ・ウォーホルの「The Factory」(アートの大量生産という意味を込めての命名)のうち、
特に1964年から使ったスタジオで、
エレベーターから始まり壁はすべて銀色、銀色の長方形のヘリウム風船が浮かぶ空間であった。
ここでウォーホルは、シルクスクリーン以外にも、靴、映像、彫刻などありとあらゆる作品を精力的につくっていたが、
と同時に、多くのアーティストたちやセレブリティたちが集まるかっこよく憧れの社交の場となっていった。
ウォーホル自身は殆どやらなかったようだがドラッグもあふれ、
次第にはちゃめちゃとなり、世間からも眉をひそめられるようになる。
しかし、この時期がウォーホルの黄金期とも言え、
マリリン・モンロー、エルヴィス・プレスリー、ムハマド・アリ、エリザベス・テーラー等のシルクスクリーン作品や、
キャンベル・スープ、Brilloの箱、コカ・コーラの絵、
エンパイア・ステートビルディングを8時間5分撮り続けた映像作品などもこの時期につくられていて、
アート界での地位を得ていった。
このような中、1964年の狙撃事件によりウォーホルの受けた衝撃は心身ともに相当なものだった。
それまでは何でもありだったファクトリーには厳重なセキュリティがはられるようになり、
お祭り騒ぎは終わった。
アンディは、この事件以降の自分の人生について、いつもテレビ映像を見ている気分、と言っている。
その後のアンディ・ウォーホルは
Interview誌の発行など画期的な取り組みもしたものの、
リッチなパトロンのもと、肖像画のシルクスクリーン作品を大量に生み出すこと、
お金を儲けることに注力し、
次第に「business artist」との評価を受けるようになっていく。
バスキア等の若手アーティストに刺激され、
1980年代には再び絵筆をとってみるようになり、
1984-1986にはバスキアと共同で50枚の作品を作成。
しかし、世間の評価はつれないものであった。
日本での1983年のTDKのCMとはアンディ・ウォーホルにとってこのような時期に撮られたものである。
おわりに
このような背景があって、
私たちの中のアンディ・ウォーホルは商業主義的な印象が大きく、
POPアートの巨匠というタイトルとうまく
辻褄をあわせることが難しくなっているのではないか。
映画でもアンディ・ウォーホルの描き方はさまざまである。
イーディ・セジウィックを主人公にした「ファクトリー・ガール」では
結構「いやな奴」として登場する。
(ただ、シルバー・ファクトリーの様子がすばらしく美しく撮られているのと、
ガイ・ピアースの演技がアンディ・ウォーホルそっくり)
「アンディ・ウォーホル/スーパースター」では
多数の友人や家族たちがインタビューに答えており、
あたたかみあるコメントをしている。
いずれにしても、エピソード満載のこのアーティストへの世間の興味はつきず、
テレンス・ウィンター脚本、ジャレッド・レト主演の映画「Warhol」が企画されているようである。
冒頭述べた通り、アンディ・ウォーホルの作品や生き様全体をみると、
その絶対的な美的センスがわかってくる気がする。
映画がその手助けになってくれる。
( Originally Posted on 2016-10-20 )